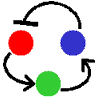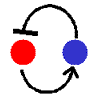実験生物学者のための反応拡散系
文責:尾崎 淳
生物をどう理解するか
科学者には、「わかった!」と感じるツボの違いで、2タイプあるそうな。
1つは「WHAT型」の人、もう1つは「HOW型」の人。
WHAT型の興味は物質的実体に、HOW型の興味は動作原理に、それぞれある。
例えて言うならば、コンピュータのハードの側面に興味があるか、ソフトの側面に興味があるか、という感じか?違うかな?
遺伝子で言えば、「遺伝子=DNA」で「わかった!」がWHAT型、「オペロン」で「わかった!」がHOW型、かな(まぁDNAには、構造それ自体にHOWが入っているから、両タイプの人に感動を与えるが・・)。
興味は人それぞれだし、理解のツボも人それぞれなので「お好きなようにどうぞ」なのだが、私は明らかにHOW型です。
分子生物学は生物の物質的基盤を明らかにしました。
これにより遺伝学・発生学・生理学などの各分野は、分子生物学という共通の言葉と手法で理解されるようになりました。
初期のころの分子生物学はWHAT型・HOW型双方の好奇心を満たしていたが、近年はめっきりWHAT型になってしまった感がある。個人的にはオペロン以降、HOW型の好奇心を満足させる概念はないのでは?とすら思う。モノーなんて30年も前に「もう分子生物学は終わった」って言っているしね。
ゲノム・サイエンスはWHAT型の極致でしょう。
この分野が現在の分子生物学の主流になっていることからして、現在の分子生物学=WHAT型であることの証だと思う。
じゃあ、HOW型の極致はなんでしょうね?モノーはオペロン説で終わりだと言ったし、私もそれに基本的には同意見だけど、もう少し完全な形で言えば、それは反応拡散機構だと言うべきだと思う。
HOW型の理解の仕方
|
|
|||||

|
また発生学ならば、例えばある器官が1cm伸びて右に曲がる現象は、確かに全ての個体で再現されるわけだから、その仕組みは遺伝子の中に情報が入っているに違いない。
しかし、遺伝子とは単なる塩基の並びであって、それをいくら調べても“1cm伸びて右”なんていう空間情報があらわに入っているはずがないのです。
たとえ視野を広げてプロモーターや遺伝子ネットワークの解析に視点を移そうが、相変わらず“1cm伸びて右”への答えは与えないのです。
そもそも、100の現象に100の遺伝子ネットワークが1対1対応しているわけではありません。
同じシグナル伝達経路が異なる場面で登場することはよくあることですが、このこと自体、特定の分子(遺伝子)の同定だけでは答えを与えないことを示しているのではないでしょうか?
ドクドク拍動したりニョキニョキ成長したりする“生物らしさ”は、分子(遺伝子)それ自体ではなく、それらとは質的に違うレベルで理解すべきものであることは明らかです。
最高の反応拡散系の解説本を目指して
これから反応拡散系の解説を始めるわけですが、書くにあたって気をつけた点があります。 それは、なるべく生物系学部レベルの知識からスムーズに振動やパターン形成が導かれるようにすることです。 最初に書いた解説ページでも言ったように、反応拡散系は、酵素反応速度論やオペロン説などの、生化学や分子生物学の常識にその基礎があります。 それが、もう一歩のところで記述が終わるか、各論のままで終わるか、で一番肝心の“生物らしさ”が出る前に話が終わってしまっているだけなのです。 生物系の科目では物理・化学系に比べ、内容が各論や記載的になる傾向があります。 これは学問の性質上しようがないことではあるが、理論的な科目ですらそのような体裁であるならば問題です。 本来、“理論”なるものは体系的だとか一貫性だとかが、その基本精神にあるハズです。 その理論が、各論の羅列に終わっているようでは、お粗末という他ないでしょう。
アウトラインは次のようになっています。 Ι は、内容自体は教科書に載っているものです。ただし、ここまで見通しよく体系的に書いてある本はないと思います。 ΙΙ から、生物系科目としては新しい内容になります。ここの記述も、物理化学系の本ですら、ここまで明快に書いた本はないと思います。
Ι フィードバック |
↓ |
Ι 双安定系(遺伝子スイッチ) |
↓ |
ΙΙ 振動・興奮現象、パターン形成 |
誰もが認める最高の物理学者ファインマンは、説明していて相手が理解できないでいるとき、「ごめん、僕はまだ完全に理解していないようだ」と言ったそうな。
このページを読んで反応拡散系を理解できなければ、それは私の理解不足が原因であって、あなたの責任ではありません。
この方面に関心が強い人ならともかく、正直、一般の実験生物学者に薦められる反応拡散系の解説本はありません。
私自身いろいろ読みましたが、これは解かりやすい、と感心させられた本はほとんどありませんでした
(大抵は数理解析をして「とりあえず数式上そうなるんだよ」といった感じ。全くイメージ湧かないですよね、そんなの。)。
だから、この解説ページを書いたのです・・最高の反応拡散系の解説を目指して。